臨床現場の皆さんへ:研究は「振り返り」の一歩です
臨床で働く皆さんは、日々患者さんと向き合いながら、多くの書類作成に追われていることでしょう。中には、「研究なんて興味がない」「研究はよくわからない」と感じている方もいるかもしれません。しかし、私はあえてお伝えしたいのです。「臨床で患者さんと向き合っている方こそ、臨床研究に取り組むべきです。」
研究は「自分の臨床を振り返る機会」
臨床の現場では、時間に追われるあまり、治療がルーチンワーク化したり、自分に都合の良い解釈をしてしまったりすることがあります。例えば、
- 脳卒中患者のリハビリで:「この部位の梗塞なら、この症状が出るから、リハビリはこの方法で大丈夫だろう。」
- 人工膝関節置換術後の患者で:「痛みの原因はよくわからないけど、ADLは改善しているから問題ないだろう。」
こうした場面では、過去の経験に頼り、無意識のうちに「こんな感じで大丈夫だろう」と判断してしまうことが増えてしまいます。
研究は「臨床の感覚」を確かめる手段
もちろん、臨床経験や感覚はとても大切です。しかし、一度立ち止まって「自分が提供している治療は本当に患者さんのためになっているのか?」「最善の治療なのか?」を振り返ることも重要です。これを実現するための手段が臨床研究です。
- 「こういう患者さんはこんな経過を辿るはず」
- 「この治療はこの患者に効果的なはず」
このような自身の感覚や経験が本当に正しいのかを、統計やデータで確認し、自信を持って臨床に臨むための確認作業が研究です。
研究は「新たな発見」だけではない
「研究」と聞くと、iPS細胞のような画期的な発明を想像するかもしれません。しかし、実際には多くの臨床研究は臨床家の経験や感覚が本当に正しいかを確認する作業です。言い換えれば、自分が行っている治療やケアを「振り返り」「検証」し、より良い医療の提供につなげるためのツールなのです。
臨床研究は特別な人だけが行うものではありません。日々患者さんと向き合っている皆さんこそ、その経験をデータとして振り返り、確認し、自信を持って治療にあたるために、研究に取り組んでみませんか?
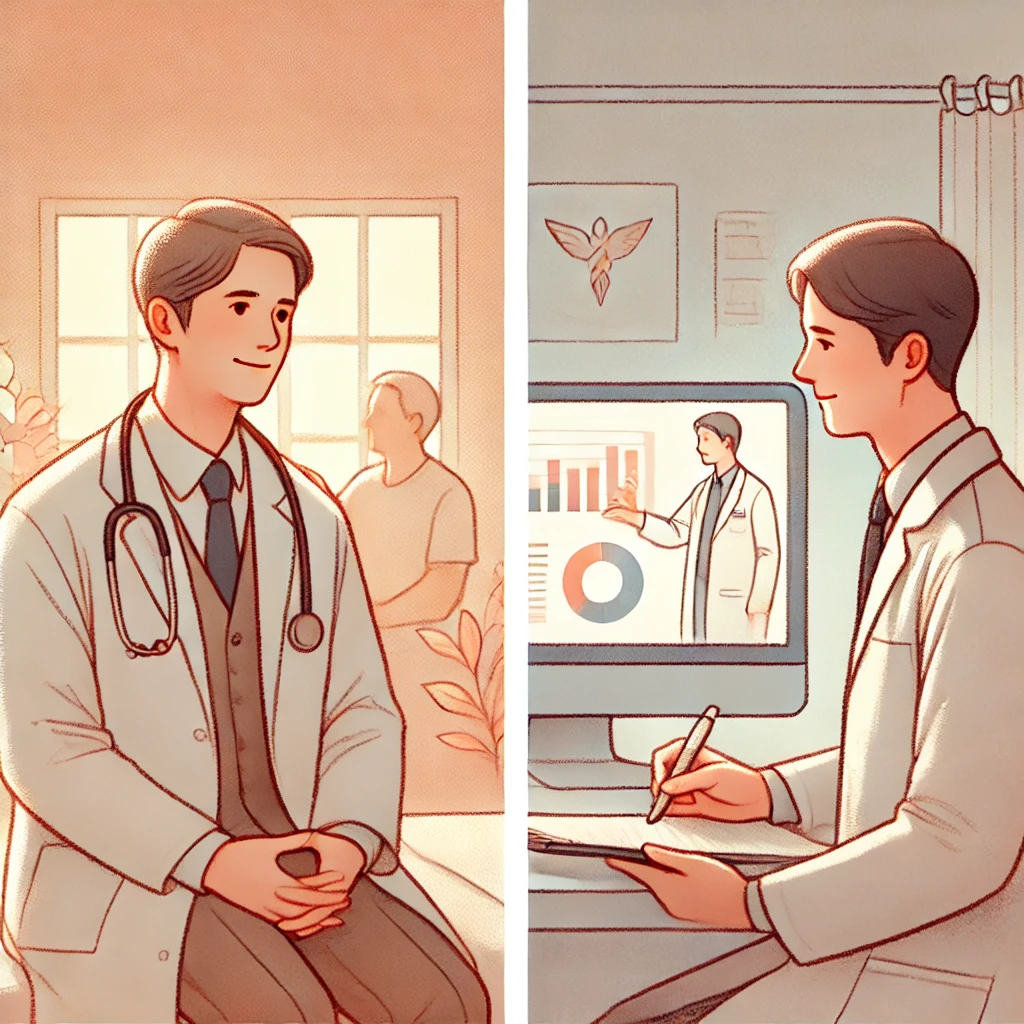


コメント